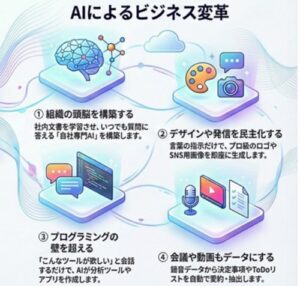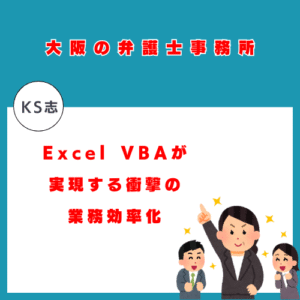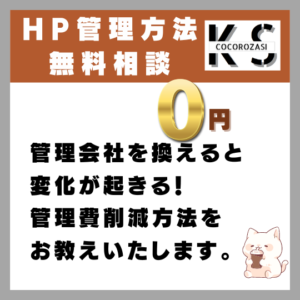タイムカードシステム、本当に「特別」ですか?
従業員の皆様の労働時間を正確に把握し、
適切な給与計算を行うためのタイムカードシステム。
多くの企業で導入されていますが、
その計算方法は意外と複雑ですよね。
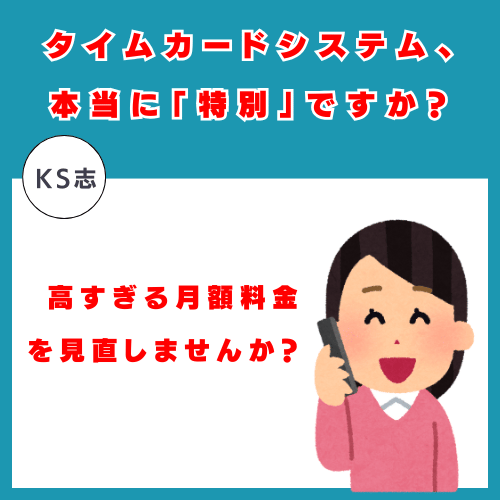
例えば、
- 始業時刻の10分前から打刻しても、定時までは残業としてカウントしない。
- 終業時刻後、15分未満の残業時間は切り捨てる。
- 深夜22時から翌朝5時までは深夜割増を適用する。
- 休日出勤の場合は、基礎時給に加えて休日割増を適用する。
など、会社ごとに独自のルールが定められているケースは少なくありません。
こうした「ちょっと特殊な計算ルール」は、市販されている一般的な勤怠管理システムでは対応しきれないことがあります。
「うちの会社のルールは特別だから、
既製のシステムじゃダメなんだよ」と考え、
Excel VBA(Excelの機能を拡張・自動化するプログラミング)を使って、
オーダーメイドの勤怠管理システムを
開発・導入している企業様もいらっしゃるでしょう。
確かに、Excel VBAを活用すれば、
かなり自由度の高い、複雑な計算ロジックを組み込んだ
システムを構築することが可能です。
「特殊な計算だからVBAじゃないと無理」
「オーダーメイドだから費用がかかるのは仕方ない」…
そう考えてしまうのも無理はありません。
しかし、ここで一度立ち止まって考えてみてください。
その「特別」だと言われている勤怠管理システム、
本当にVBAが必要なほど複雑な処理を行っているのでしょうか?
以前、ある企業様から
「特殊な勤怠計算に対応するために、専門業者にExcel VBAで構築してもらった」
というシステムについてご相談を受けたことがあります。
その企業様は、システムの保守・運用費用として、
毎月1万円以上の料金を支払い続けていました。
「特殊な計算だから、
専門的な技術が必要で、
月額費用がかかるのも仕方ない」と
その企業様は考えていらっしゃいました。
しかし、実際にそのExcelシステムの内容を
詳しく確認させていただいたところ、
驚くべき事実が判明しました。
その「特殊だ」と言われていた計算ロジックのほとんどは、
Excelに標準で備わっている
「IF関数」や「VLOOKUP関数」、「TIME関数」などを
組み合わせるだけで、十分に実現可能なレベルだったのです。
つまり、高度なVBAプログラミングは必ずしも必要ではなく、
Excelの基本的な機能を使いこなせば構築できるシステムだったのです。
にもかかわらず、その企業様は
「VBAを使った特別対応のシステムだから」という理由で、
長年にわたり高額な月額料金を支払い続けていました。
これは、非常にもったいないコスト負担と言わざるを得ません。
もちろん、会社の複雑な就業規則や賃金規定を正確に理解し、
それをExcelの計算式に落とし込む作業には、
専門的な知識と時間が必要です。
そのための初期設定費用(イニシャルコスト)が
発生するのは当然のことでしょう。
問題なのは、一度計算ロジックが完成し、
システムとして安定して稼働し始めた後も、
なぜ毎月高額な「サブスクリプション料金」を支払い続ける必要があるのか?
という点です。
システムの内容がExcel関数レベルで対応可能なものであれば、なおさらです。
本来であれば、最初の
「特殊な計算方法を正確にシステムに反映させるための初期設定費用」を支払えば、
その後は、法改正や就業規則の変更で計算方法の修正が必要になった場合や、
予期せぬトラブルが発生した場合に、
都度対応費用を支払う(スポット契約)、
あるいは、そうした万が一の事態に備えた
年間保守契約(トラブル対応込み)を結ぶ、
といった形が合理的ではないでしょうか。
もし、あなたが現在、
オーダーメイドの勤怠管理システムを利用していて、
「特殊対応だから」という理由で高額な月額保守費用を支払っているなら、
一度そのシステムの内容と契約形態が本当に見合っているのか、
見直してみることを強くお勧めします。
信頼できる業者であれば、システムの実際の複雑さを正直に評価し、
過剰な月額料金を請求するのではなく、
実態に合った適切な料金プラン
(例えば、初期設定費用+必要な時だけサポートを受けるスポット契約や、
手頃な年間保守契約など)を提案してくれるはずです。
もし、「うちのシステムも、もしかしたら…?」と感じたり、
現在の業者との契約内容に疑問を感じているのであれば、
セカンドオピニオンを求めてみるのも良いでしょう。
例えば、**「KS志」**のような、
システムの内容をしっかりと見極め、
お客様にとって最適な解決策と
正直な料金体系を提案してくれる業者に
相談してみるのも一つの手です。
「特殊だから」「オーダーメイドだから」
という言葉に思考停止せず、
本当にそのシステムとコストが見合っているのか、
ぜひ一度、冷静に検討してみてください。
専門家の視点で見直すことで、無駄なコストを大幅に削減し、
より効率的な業務運営を実現できるかもしれません。
お問い合わせ
AI活用を教える会社、社員のAIスキルを高める「KS志」

サービス内容
1対1のAI活用個別指導、業務効率化コンサルティング、各種セミナー、デジタル名刺制作

特に得意なこと
Geminiをはじめとする最新AIツールの業務への落とし込み、Excel VBAから始めるDX推進

対象
東大阪市を中心とした中小企業、
個人事業主の皆様